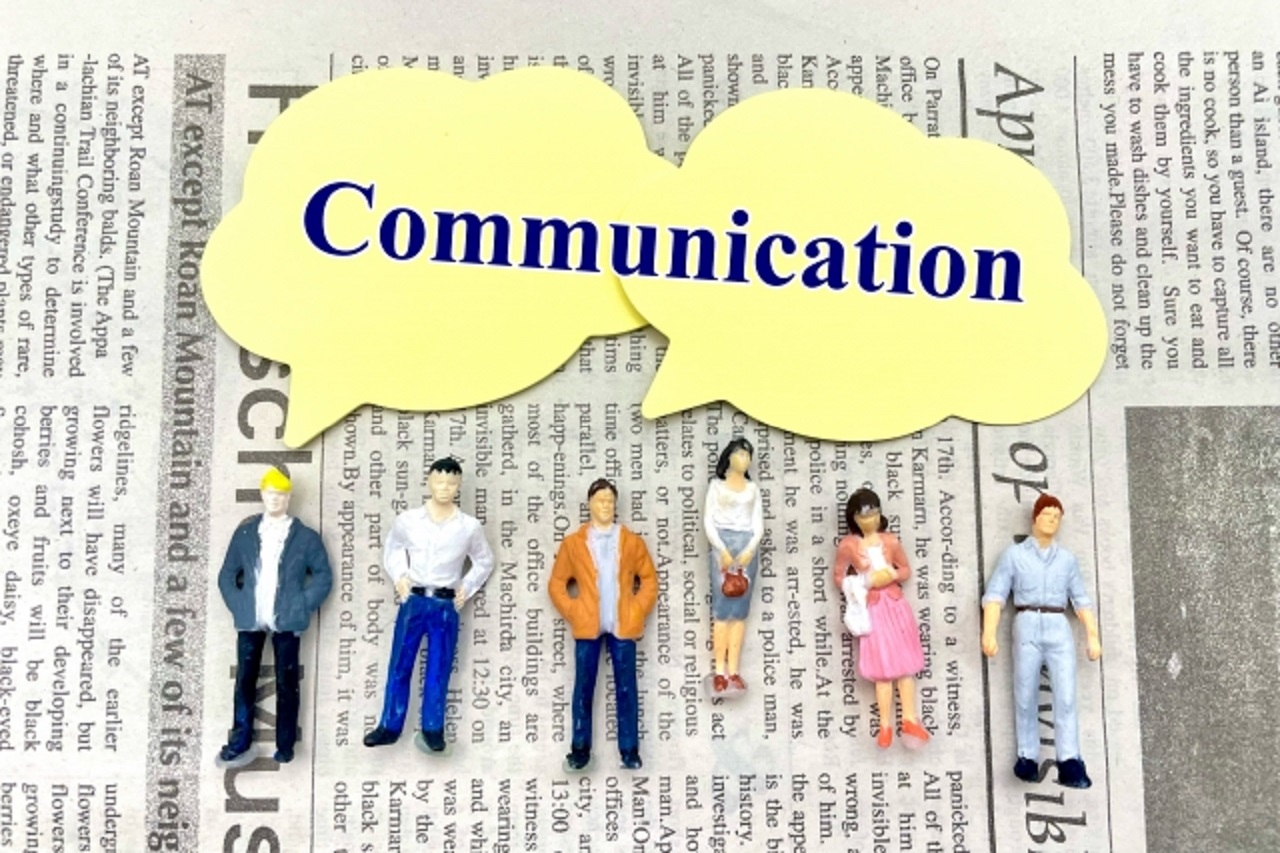言葉を尽くしても、伝わらないことがある。
むしろ、説明すればするほど、肝心な“核”がぼやけてしまう。
そんな経験はありませんか?
それは、私たちが「言葉で伝える」ことに偏りすぎて、「言葉になる前の部分」に意識が向いていないからかもしれません。
アート、デザイン、創作、あるいはビジネスのブランディングでも、本質的な力を持っているのは“コンセプト”と呼ばれる、言語と非言語のあいだにあるものです。
この記事では、ボードゲームや創作における「コンセプト力」を起点に、言葉を超えた伝達の仕組みを探り、読者の皆さん自身の“非言語コミュニケーション力”を再起動する視点をお届けします。
言葉の前にある“核”をつかむ
言語化以前の感覚が、すべての発信の起点になる
アイデアが「いい」と感じる瞬間は、たいてい説明できません。
「なんか、いい」「これ、好き」——そんな直感的な感覚は、まだ言葉になる前の“発想のコア”です。
実は、優れたクリエイターや企画者は、この「言葉にしきれないもの」を大切にしています。
言葉にすることよりも、“感じたまま”を保ちながら他者と共有する技術こそが、真の伝達力になるのです。
たとえばボードゲーム『コンセプト』では、言葉を一切使わずに、アイコンの組み合わせだけでお題を伝えます。
「映画のキャラ」「自然現象」「道徳的な概念」などを、抽象記号でどう表現するか。
このプロセスは、感覚を他者に委ねながら、「どこまで伝わるか」を試す対話でもあります。
言葉の手前にある“共感の回路”を信じる。
それが非言語のコミュニケーションの起点になるのです。
フクハナのボードゲーム紹介 :No.253『コンセプト』
説明できなくても「伝わる」は可能か?
「説明しなくては伝わらない」
そう思い込んでいる人は少なくありません。
しかし、本当に深いところで人を動かすものは、「なんとなく惹かれる」「直感的にわかる」ものです。
それは理屈よりも、空気・感情・雰囲気といった、非言語的な要素によって構成されています。
『コンセプト』では、プレイヤーが自分なりの“象徴体系”を組み立て、それを他者に“感じ取ってもらう”形で伝達が行われます。
これはまさに、プレゼン・ブランド構築・創作全般で問われる「言葉にしない力」の訓練とも言えるでしょう。
言葉を補助的なものとし、言葉に至る前の“発想の呼吸”を信じることで、伝える力の質は大きく変わっていきます。
AI時代に求められる「言語化の一歩手前」の能力
AIは、膨大な情報を高速で処理し、論理的に言語化してくれます。
だからこそ、人間の役割は「まだ言語化されていない何か」を感じ取り、創り出すことへとシフトしています。
言語化の手前にある「あいまいな感覚」や「場の雰囲気」、そして「相手の表情から感じる違和感」など。
これらは、AIが完全に代替することが難しい領域です。
『コンセプト』のような言葉を使わないゲームは、こうした“言語前の世界”を遊びの中で体験させてくれます。
感じたことを、どう伝えるか。
それ以前に、どんな風に「感じているか」。
今、あらゆる仕事や人間関係において、“感じ方のチューニング”が問われているのです。
言語外の伝達が生きる現場とは
職場やプロジェクトでの「共感の土台」づくり
会議や打ち合わせで、「言っていることは正しいのに、なぜか納得感がない」
そんな場面に出会ったことはないでしょうか。
これは、情報の伝達はできていても、“感覚の共有”ができていないときに起きるズレです。
言葉やロジックの奥にある、「なぜそれを言うのか」「なぜその方向に進みたいのか」といった根っこの部分。そこが共有されていないと、人の心は動きません。
『コンセプト』のように、言葉を使わずに伝えるゲームでは、まず「相手がどう感じるか」を想像することが前提になります。
これは、まさに「相手の視点に立つ」=共感をベースにしたコミュニケーションの練習と言えるでしょう。
プロジェクトの初期段階、理念共有、ビジョン設定など、明文化しにくい内容ほど、非言語的な理解が重要になります。
感じ方の共通言語を育てることが、後の判断スピードや連携の質に直結するのです。
創作や企画で活きる“伝える力”の再定義
文章を書く、デザインをつくる、商品を企画する——
これらの創造的な営みは、すべて「誰かに何かを伝える」ことを目的としています。
ただし、伝えるとは“説明する”ことではありません。
むしろ「説明しすぎると魅力が消える」領域が、創作の世界にはたくさんあります。
“伝えたい核心”を、相手が自分で発見できるように設計すること。
つまり、「余白を残す」ことが、本当の伝達力だとも言えるのです。
『コンセプト』でアイコンを選び、配置し、意図を込めて相手に委ねるように、
クリエイターや企画者も、言葉やデザインに“意味を宿す”技術を磨いています。
非言語の伝達は、単なるスキルではなく、「相手を信じて手渡す姿勢」そのものでもあります。
これは、すべての創造に通じる深いあり方なのです。
チームでの対話と“沈黙”の活用
チーム内で何かを決めるとき、あえて言葉を抑えて「考えを巡らせる沈黙」が生まれる瞬間があります。
この沈黙をどう扱うかが、そのチームの成熟度を物語ります。
『コンセプト』では、提示された記号を見ながら、全員が静かに“考える”時間が流れます。
その沈黙は、決して気まずさではなく、思考と共感の交差点のような空気です。
ビジネスや教育の現場でも、この「沈黙を共にする力」が見直されています。
すぐに答えを出さず、思考の余白に浸り、感じたことを大事にする時間——
それが、深い合意形成や納得感のある決断を生みます。
言葉にしない選択。
沈黙という対話。
そんな非言語の領域を信じることで、関係性の質は格段に変わるのです。
結び|“言葉にしない力”が世界を変える
私たちは、常に「伝えなきゃ」と思っています。
でも、本当に大切なものほど、言葉にならない形で伝わっていくのかもしれません。
『コンセプト』というシンプルなボードゲームには、
言葉がなくても人と通じ合える可能性が、見事に詰まっています。
これからの時代は、説明や正しさよりも、
「感じたものを、感じたまま渡せる力」——そんな“言葉にしない力”が価値を持つのではないでしょうか。
もしあなたが今、伝えることに悩んでいるなら、
言葉になる前の“感覚”に立ち戻ってみてください。
そして、伝えることは「任せること」でもあるということを、思い出してみてください。
きっとその先に、今までとは違うつながり方が待っているはずです。