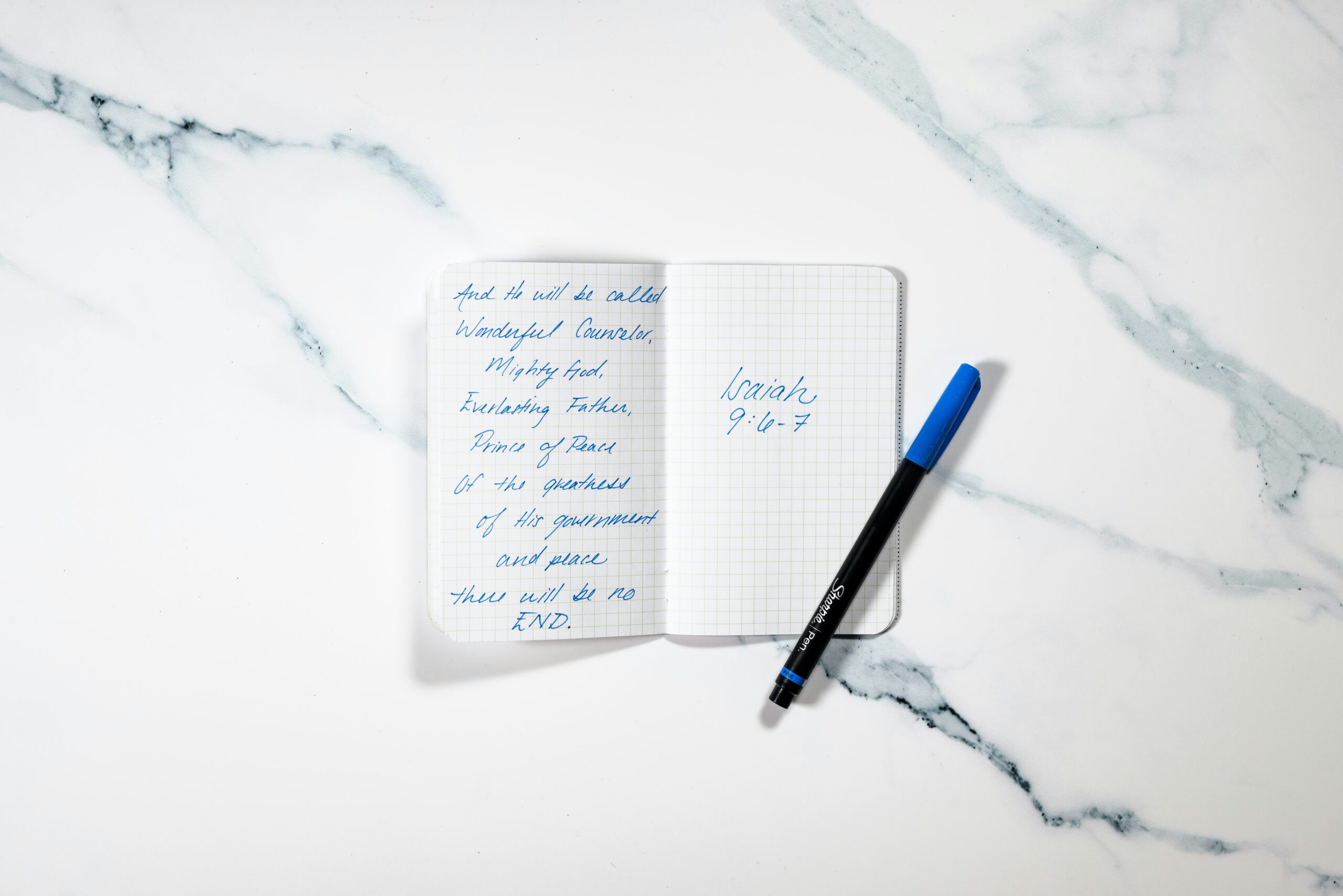「なんで“アイスクリーム”を説明するのに、“冷たくて甘くて、夏に食べるお菓子”って言うの?」
はじめて「ボブジテン」を体験したとき、そんな戸惑いと笑いが入り混じった声が、あちこちで聞こえてきました。
外来語を使わずに、外来語そのものを説明する──。それは、ただの言葉遊びではなく、私たちの思考回路や価値観の“前提”を問う体験でもあります。
「なんでそれが当たり前だと思っていたんだろう?」という気づきが、言葉の選び方や表現の幅を広げるきっかけになるのです。
AIが進化し、翻訳や要約が瞬時に行えるようになった時代だからこそ、「自分の言葉で伝える力」や「他人の感覚を想像する力」は、ますます大切になってきています。
ボブジテンという“ゆるくて奥深い”ゲームを通して、あなたの中に眠る“言語の野生”を目覚めさせてみませんか?
言葉の不自由が“自由”を生む|ボブジテンという構造
外来語を使わないルールが思考を耕す
ボブジテンの基本ルールはとてもシンプル。「外来語を、日本語だけで説明する」。ただそれだけなのに、プレイしてみると驚くほど脳が活性化されます。
普段は無意識に使っている言葉も、いざ“言い換え”が必要になると、私たちは「本質」を探り出すしかありません。
「アイスクリーム」=「冷たくて甘い食べ物」「スプーンですくって食べる」「お祭りのときに買うことがある」──。
そうやって、体験や感情を手繰り寄せながら、相手に伝わる説明を試みるうちに、自分でも気づかなかった“意味の層”に触れていきます。
言葉を縛るルールがあるからこそ、逆に自由な発想が生まれる。ボブジテンは、まさにその原理を体感させてくれる知的な遊びなのです。
【ボドゲ】カタカナ語を使わずに説明シタマエ!【ボブジテン】
相手の“辞書”を想像する力
このゲームでは、説明者と回答者の“思考のズレ”も醍醐味のひとつです。
たとえば「ハンバーガー」を「丸い形」「お肉とパン」「お昼によく食べる」と説明しても、「おにぎり」や「サンドイッチ」と勘違いされることもあります。
なぜなら、相手の“辞書”には、別の感覚や価値観が記憶されているからです。
ここで求められるのは、「自分の説明が正しいか」ではなく、「相手の辞書ではどう受け取られるか?」という視点の転換。
これはまさに、ビジネスでも日常でも大切な“共感力”や“相手目線”のトレーニングになります。
相手の“前提”を読み取り、自分の表現をチューニングする──そのプロセス自体が、対話の本質とも言えるのではないでしょうか。
AI時代の“ことばの地力”を育てる
今、AIが文章を生成し、翻訳を行い、会話まで支援する時代に突入しています。そんな中で、人間にしかできないことは何でしょう?
それは、おそらく「意味を選ぶ力」や「相手の気持ちを読む力」、そして「文脈を想像する力」だと私は思います。
ボブジテンのような“制限つきの言語遊び”は、そうした人間的な能力を楽しく、自然に育ててくれます。
たとえば、ChatGPTに「パフェって何?」と尋ねれば、即座に完璧な説明が返ってきます。でも、友人と笑いながら、「あれって、なんかこう、スイーツ界の宝石箱だよね」なんて話しているときの感覚は、やはり人と人の間にしかないものです。
つまり、言葉の“意味”は、辞書ではなく関係性の中に宿るということ。
ボブジテンは、その原点を思い出させてくれる装置でもあるのです。
“遊び”が創る共感の場|ボブジテンの応用シーン
会議やワークショップのアイスブレイクに最適
ボブジテンは、単なる娯楽ではありません。企業研修やチームビルディングの場でも、効果的な“アイスブレイク”として活用されています。
特に初対面同士の場面では、共通の言語感覚やユーモアのセンスを探るうえで、非常に有効です。
外来語禁止というルールが参加者全員に平等なハードルを与え、緊張感よりも“笑い”を生む。失敗しても評価されない、むしろ“面白さ”として歓迎される──。その空気が、関係性の緊張をほどきます。
また、ボブジテンは「相手の話をよく聴く」「少ない情報から意味を探る」という“受け取り方”のトレーニングにもなります。これは、日常的な対話の質を高める上でも非常に価値あるスキルです。
世代を超えてつながれる“感覚ゲーム”
言葉のゲームというと、どうしても語彙力や知識量に依存する印象がありますが、ボブジテンはその限界をやさしく飛び越えます。
お年寄りは「ちゃぶ台」「カセットテープ」など昭和感覚で説明するかもしれませんし、子どもは「鬼滅に出てたやつ」などアニメで表現するかもしれません。
そのズレが、むしろ会話の種になり、思わぬ共通点や世代差を笑い合う場面に発展するのです。
“違い”を否定せず、“面白がる”。
その柔軟な感覚は、今の社会にこそ必要とされるものではないでしょうか。
“わかってもらえた”という感覚の再発見
説明役が「これで伝わるかな…」と緊張して話し、聞き手が「え?それってアレでしょ!」とピタリと言い当てる。
そんな瞬間には、場に小さな“共鳴”が起こります。
それは、ただゲームに正解したというだけではなく、「自分の感覚が、相手とつながった」という確かな実感です。
この感覚こそが、私たちが本当は言葉に求めているものなのかもしれません。
正解かどうかより、共鳴があるか。
言葉を“伝える”ことの本質は、情報ではなく共感にある──そう教えてくれるのが、ボブジテンなのです。
まとめ|言葉の“余白”を楽しむ感性をもう一度
ボブジテンを遊ぶと、語彙が増えるとか、表現力が鍛えられるとか、そんな実利的なメリットももちろんあります。
でも本質はそこではなく、「言葉を選ぶって、楽しいことだったんだ」と思い出すことにあるのではないでしょうか。
完璧な説明じゃなくていい。
うまく言えなくても、伝わるときは伝わる。
むしろ、制限があるからこそ、私たちは自由な発想を取り戻せるのです。
「伝える」とは、情報の輸送ではなく、感性の橋を架けること。
ボブジテンは、その橋を遊びながら架けるための、美しくて奥深い“言語の実験場”なのかもしれません。
あなたも今日、誰かにひとこと。
「外来語なしで、これ、説明できる?」と問いかけてみてはいかがでしょうか。
きっとそこには、新しい対話の風が吹くはずです。