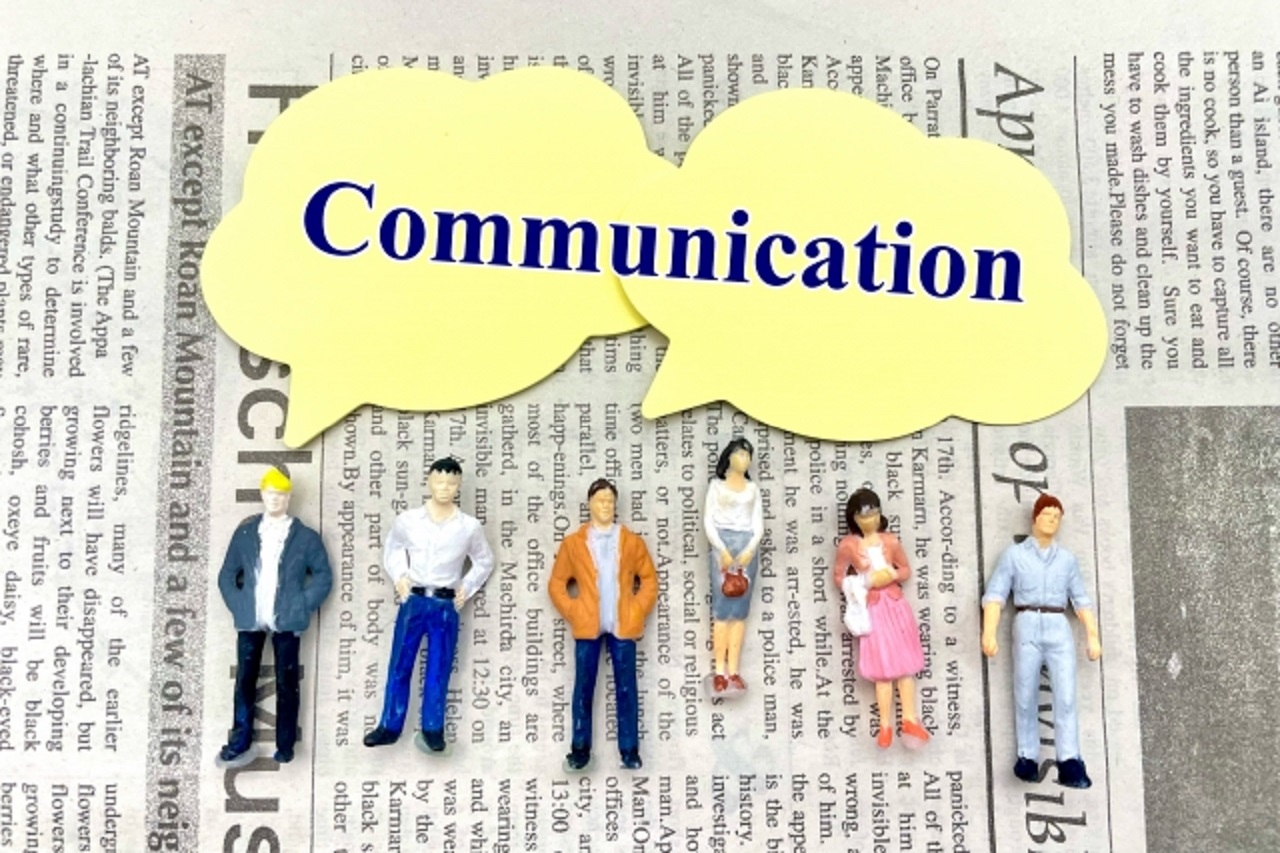ハラスメント対策というと、マニュアル作成や研修が真っ先に思い浮かびます。
しかし、それらは往々にして「やらされ感」が伴い、現場の行動変容につながらないことも少なくありません。
一方で、ボードゲームやシミュレーションゲームは、参加者が自然にルールを共有し、相手の立場を想像しながら行動する環境をつくります。
そこには、職場で必要とされる「心理的安全性」や「相互理解」を促す要素が詰まっています。
この記事では、ゲーム的思考や実際のゲーム活用事例を通じて、ハラスメント対策をより効果的で持続可能なものにする方法を探ります。
ハラスメント対策とゲームの意外な共通点
ルールがあるから自由に動ける
ボードゲームには明確なルールがあります。
これにより、参加者は安心して自分の行動を選び、発言できます。
職場でも、行動指針やコミュニケーションルールが明確であれば、不安や猜疑心が減り、健全なやり取りが可能になります。
ルールがなければ「これを言ったら怒られるかもしれない」という恐れが蔓延し、対話が萎縮します。
逆にルールが透明で公平なら、全員が対等な立場で関わる土台が生まれます。
ゲームは、この「安心できる枠組み」の価値を体感させる格好のツールです。
プレイヤー視点で役割を入れ替える
多くのゲームでは、プレイヤーが異なる立場や役割を体験します。
ハラスメント問題の背景には、相手の立場を想像できない「視野の固定」があります。
役割を入れ替えて体験することで、相手の視点から物事を見る力が養われます。
たとえば交渉型ゲームでは、立場や利害の異なるキャラクターを演じます。
これにより、「相手がなぜその行動を取るのか」という理解が深まり、実際の職場でも安易な決めつけを減らす効果が期待できます。
安全に失敗できる場をつくる
ゲームでは、失敗が許されます。
むしろ失敗から学ぶことが重要で、次の手をより良くするヒントになります。
職場では、失敗が即評価や処罰につながる環境がハラスメントの温床となります。
安全に試行錯誤できる場を、ゲーム形式で疑似体験することで、失敗を糧にできる文化を広げられます。
これが心理的安全性の醸成につながります。
ゲームが生み出す心理的安全性の仕組み
フィードバックが即時で平等
ゲームでは、行動に対する結果がすぐに返ってきます。
さらに、そのフィードバックはプレイヤー全員が共有できるため、透明性があります。
職場のフィードバックも、即時性と透明性があれば、陰口や誤解が減り、健全な関係が保たれます。
また、ゲームでは役職や経験年数に関わらず同じルールで評価されます。
この平等性が、権力差による萎縮を和らげる効果を持ちます。
協力型ゲームで養う共通目標意識
協力型ボードゲームでは、プレイヤー全員が同じゴールに向かいます。
全員が勝者になれる状況を作ることは、職場の雰囲気改善に直結します。
共通の成功体験は信頼関係を強化し、ハラスメントの抑止にもつながります。
協力ゲームの中で発揮される「役割分担」「助け合い」「情報共有」は、そのままチームマネジメントの基本スキルとなります。
ゲーム的アプローチを職場に導入する方法
小さく試し、大きく広げる
いきなり全社研修として導入するのではなく、小規模なチームや部署で試すのがおすすめです。
参加者の感想や行動の変化を観察しながら、徐々に範囲を広げます。
短時間で終わる軽いカードゲームやワークショップ形式から始めると、抵抗感が少なくスムーズに浸透します。
AIとの組み合わせで効果を可視化
AIは参加者の発言や選択パターンを記録し、傾向を分析するのに適しています。
これにより、ハラスメントリスクの高いコミュニケーションや、改善が必要な領域を可視化できます。
データと体験が組み合わさることで、対策はより具体的で効果的になります。
結び:遊びから職場を変える
対話と信頼はルールから生まれる
ゲームは、ルールの中で自由を楽しむ文化を育みます。
この文化が職場に根付けば、相互理解と心理的安全性が高まり、ハラスメントは発生しにくくなります。
研修や規定づくりだけでは得られない「体験からくる納得感」を、ゲームは提供します。
遊び心を通じて、職場をもっと安心して働ける場所に変えていく――その一歩は、テーブルの上から始まります。